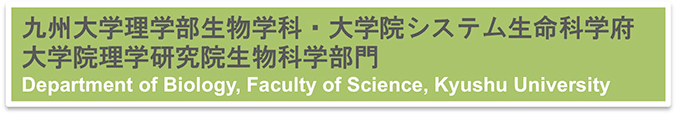第24回九州大学理学部生物学科公開講座
【日時】2025年8月8日(金)13:30〜16:00
【場所】オンライン同時配信
【対象】高校生および市民
【定員】約200名
【参加費】無料
【主催】九州大学大学院理学研究院・生物科学部門
【連絡先】生物学科教育支援室(担当 中條信成; 092-802-4269)
【参加申込】下のボタンを押して表示されるフォームから登録をお願いします。

本年度の公開講座は終了しました。
![]() 公開講座フライヤー
公開講座フライヤー
講演内容
高校生の受講者が多いため、最初に九州大学理学部生物学科の紹介を行った後に以下の2名の先生方による講演を行います。
なぜ植物の気孔には葉緑体が存在するのか?
祢冝 淳太郎(植物生理学研究室・教授) Negi Juntaro, Professor
 葉緑体は植物細胞を最も特徴づける細胞内小器官であり、植物の独立栄養を支えています。例えば、葉肉細胞の葉緑体は、植物の光合成において中心的な役割を果たしています。一方、植物のガス交換を担う気孔(孔辺)細胞にも葉肉細胞の葉緑体より小さく、デンプンが溜まったユニークな葉緑体が存在します。しかし、その機能については1世紀以上、研究者の間で議論されているものの結論が出ておらず、また成り立ちに関しては全くわかっていませんでした。近年、私たちは気孔葉緑体が単なる光合成装置ではなく、光やCO2などの環境情報を感知し、気孔の開閉を調節する司令塔として働く可能性を見出しました。なぜ、気孔には葉緑体が存在するのか、気孔葉緑体の機能やその成り立ちについて、最新の知見を交えて紹介したいと思います。
葉緑体は植物細胞を最も特徴づける細胞内小器官であり、植物の独立栄養を支えています。例えば、葉肉細胞の葉緑体は、植物の光合成において中心的な役割を果たしています。一方、植物のガス交換を担う気孔(孔辺)細胞にも葉肉細胞の葉緑体より小さく、デンプンが溜まったユニークな葉緑体が存在します。しかし、その機能については1世紀以上、研究者の間で議論されているものの結論が出ておらず、また成り立ちに関しては全くわかっていませんでした。近年、私たちは気孔葉緑体が単なる光合成装置ではなく、光やCO2などの環境情報を感知し、気孔の開閉を調節する司令塔として働く可能性を見出しました。なぜ、気孔には葉緑体が存在するのか、気孔葉緑体の機能やその成り立ちについて、最新の知見を交えて紹介したいと思います。

昆虫の必須共生微生物を入れ替える
細川 貴弘(生態科学研究室・准教授) Hosokawa Takahiro, Associate Professor
体内に共生微生物を保持し、共生微生物から供給される栄養分に強く依存して生活している昆虫はたくさんいます。代表的な例であるアブラムシのなかまは体内にブフネラとよばれる共生細菌を保持しており、ブフネラが合成する必須アミノ酸を使って成長や繁殖をおこなっています。アブラムシに抗生物質を注射してブフネラを殺してしまうと、アブラムシも生きていけません。このような共生微生物を必須共生微生物と呼んでいます。ほとんどの場合、必須共生微生物は昆虫の体に高度に統合されているので、昆虫個体間で共生微生物を入れ替えることは困難でした。ところが私はカメムシ類の必須共生微生物は例外的に入れ替えが自由にできることを発見しました。今回の公開講座では、昆虫の必須共生微生物について概説し、カメムシ類の必須共生微生物の入れ替え実験から得られた研究成果を紹介します。

過去の公開講座
2013年(平成25年)第12回:川畑, 市川
2014年(平成26年)第13回:伊藤, 池ノ内
2015年(平成27年)第14回:射場, 寺本
2016年(平成28年)第15回:谷村, 佐竹
2017年(平成29年)第16回:矢原, 高橋
2018年(平成30年)第17回:舘田, 祢冝
2019年(令和元年)第18回:釣本, 粕谷
2020年(令和2年)第19回:斎藤, 手島
2021年(令和3年)第20回:松尾, 仁田坂
2022年(令和4年)第21回:立田, 藤原
2023年(令和5年)第22回:熱田, 吉村
2024年(令和6年)第23回:石原, 佐々木