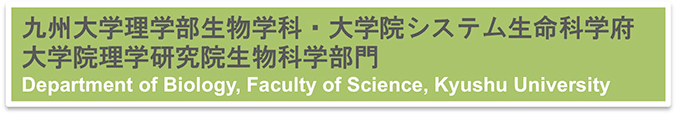第23回九州大学理学部生物学科公開講座
【日時】2024年8月9日(金)13:30〜16:00
【場所】オンライン同時配信
【対象】高校生および市民
【定員】約200名
【参加費】無料
【主催】九州大学大学院理学研究院・生物科学部門
【連絡先】生物学科教育支援室(担当 中條信成; 092-802-4269)
![]() 公開講座フライヤー
公開講座フライヤー
講演内容
高校生の受講者が多いため、最初に九州大学理学部生物学科の紹介を行った後に以下の2名の先生方による講演を行います。
中枢神経回路での情報処理を遺伝子の働きから解き明かす -記憶を忘れるメカニズム-
石原 健(分子遺伝学研究室・教授) ISHIHARA Takeshi, Professor
動物は刻々と変化する環境に適応した行動をとることができます。このとき、過去の経験によって得られた記憶によって行動を変化させることもできます。このような高度な情報処理も、受精卵がもつ遺伝情報によってプログラムされています。私たちは、遺伝学を使って、どの遺伝子がいつどこでどのように働いて情報処理を制御しているかを、明らかにしようとしています。
私たちの研究室では、様々な情報処理のうち、記憶の忘却のメカニズムに焦点をあてて、線虫の匂い学習をモデルとして研究をしています。線虫は、単純な神経回路をもち、遺伝学や顕微鏡による神経活動測定などが可能であるため、どのような遺伝子がいつどこでどのように働いて、神経回路における忘却を制御しているかを明らかにすることができます。記憶を忘れるメカニズムを中心に、遺伝子が神経回路において情報処理を制御する仕組みについて紹介します。

図の説明:線虫の中枢神経系とその活動
植物が春を予測する「記憶」のメカニズム
佐々木 江理子(数理生物学研究室・准教授) SASAKI Eriko, Associate Professor
動物と異なり、動き回ることができない植物は、自分が置かれている環境で生き延びるために様々な仕組みを進化させてきました。その一つに、毎年やってくる冬の長さや、冬が始まってからどれくらい時間が経つかを記憶する仕組みがあります。冬の長さはDNAを通じて親から子へと引き継がれますが、その年の冬が始まってからの時間は毎年リセットされ、タンパク質の変化によって記録されます。このようにして植物は、住んでいる地域に春が訪れる時期を予測し、さらには、年々の気温の変化に応じて最適な時期に花を咲かせることができます。私たちは、このように植物が花を咲かせる時期を調節する仕組みを、ヨーロッパに広く見られるシロイヌナズナという植物を使って研究してきました。このセミナーでは、世界中から集められたシロイヌナズナが持つ冬の記憶を測定し、記憶を調節する仕組みを見つけ出す研究について紹介します。

過去の公開講座
2013年(平成25年)第12回:川畑, 市川
2014年(平成26年)第13回:伊藤, 池ノ内
2015年(平成27年)第14回:射場, 寺本
2016年(平成28年)第15回:谷村, 佐竹
2017年(平成29年)第16回:矢原, 高橋
2018年(平成30年)第17回:舘田, 祢冝
2019年(令和元年)第18回:釣本, 粕谷
2020年(令和2年)第19回:斎藤, 手島
2021年(令和3年)第20回:松尾, 仁田坂
2022年(令和4年)第21回:立田, 藤原
2023年(令和5年)第22回:熱田, 吉村